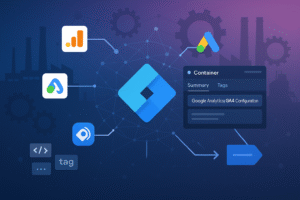はじめに
「DXって本当に効果があるのか?」「うちのような中小製造業でも営業DXは可能なのか?」
このような疑問を抱く経営者の方は多いのではないでしょうか。実際、これまでサポートしてきた中小製造業の中でも、営業DXに取り組んだものの思うような成果が得られず、途中で断念してしまう企業が少なくありません。
豪・ボンド大学の調査によると、CRM導入の半数以上が失敗に終わるというデータもあり、製造業においても同様の課題が見られます。
※CRMに関する説明は以下の記事でも紹介してます。

しかし、正しいアプローチで取り組めば、中小製造業でも確実に成果を上げることができます。今回は、当社の複数の支援実績を基にした想定ケースとして、従業員50名規模の金属加工業が営業DXによって大幅な成果向上を実現した事例を通じて、製造業における営業DX成功の秘訣をお伝えします。

※本記事の事例は、当社の複数の支援実績を基にした想定ケースです
想定企業の概要と課題
今回ご紹介する企業は、創業40年の金属加工業で、自動車部品や産業機械部品の製造を手がけています。従来は既存顧客からの受注に依存しており、新規開拓は展示会への出展と飛び込み営業が中心でした。
抱えていた課題
- 営業活動の属人化:ベテラン営業担当者のスキルと人脈に依存
- 顧客情報の散在:名刺、Excel、個人メモに情報が分散
- 営業プロセスの不透明性:進捗状況や成約率が把握できない
- 新規開拓の低効率:限られたリソースでの営業活動に限界
このような状況で、コロナ禍により既存顧客からの受注が減少し、危機感を抱いた社長が営業DXの検討を始めました。
第1回目の挑戦:失敗の要因分析
最初に取り組んだのは、大手ITベンダーが提案した高機能なCRMシステムの導入でした。しかし、この取り組みは残念ながら失敗に終わりました。
失敗の主な要因
この失敗要因は、CRM導入失敗の典型的なパターンと一致しています。
1. 現場の巻き込み不足 システム導入を決定したのは経営陣のみで、実際に使用する営業担当者の意見を十分に聞いていませんでした。オリバー・シュルツ博士の研究でも、「CRM導入失敗の70%は現場に受け入れられないこと」と指摘されています。
2. 過度に複雑なシステム選択 多機能すぎるシステムを選んだため、操作が複雑で覚えることが多く、特にITに慣れていないベテラン営業担当者にとって大きな負担となりました。
3. データ移行の不備 既存の顧客情報をシステムに移行する際、データの整理・統合を怠ったため、重複や不整合が多発し、現場の混乱を招きました。
4. 運用ルールの未整備 誰が、いつ、どのような情報を入力するのかが明確でなく、データの品質が低下。結果として「使えないシステム」という印象を与えました。
この失敗により、「やはりDXは難しい」という空気が蔓延し、一時は営業DXの取り組みが頓挫しました。
成功への転換点:3つのステップ
失敗から1年後、当社のサポートを受けながら、段階的なアプローチで営業DXに再挑戦しました。この時に採用したのが、以下の3ステップです。
ステップ1:現状分析と課題の明確化(1~2ヶ月)
具体的な取り組み
- 営業担当者へのヒアリング実施
- 営業プロセスの可視化
- 顧客データの棚卸し
- 業務フローの整理
重要なポイント このステップで最も重要だったのは、現場の声を丁寧に聞くことでした。「なぜ前回のシステムが使いにくかったのか」「どのような機能があれば業務が楽になるのか」を営業担当者全員から聞き取りました。
また、営業プロセスを細かく分解し、どの段階でどのような情報が必要なのかを明確にしました。例えば:
- 見込み客発掘:企業情報、担当者情報
- 初回訪問:課題・ニーズの把握
- 提案:技術要件、価格条件
- 成約・フォロー:契約内容、納期管理
ステップ2:小さく始める仕組み作り(2~3ヶ月)
具体的な取り組み
- シンプルなCRMツールの選定
- 最小限の機能から運用開始
- データ入力ルールの策定
- 週次の振り返りミーティング実施
選択したツール 選定したのは、クラウド型の軽量CRMシステムでした。重要だったのは以下の特徴:
- 直感的な操作性
- スマートフォンからの入力対応
- 必要最小限の機能に絞った構成
- 低価格での導入が可能
運用ルールの例
- 訪問後24時間以内の報告入力
- 毎週金曜日に進捗状況の確認
- 月末に全案件のレビュー実施
ステップ3:データ活用による営業力強化(3~6ヶ月)
具体的な取り組み
- 営業データの分析・可視化
- 成約パターンの把握
- 営業活動の改善施策実行
- 新規開拓手法の確立
データ活用の実例 蓄積されたデータから以下のような知見が得られました:
- 初回訪問から成約までの平均期間の把握
- 成約率の高い業界の特定
- 最適な訪問頻度の発見
これらの分析結果を基に、営業戦略を大幅に見直しました。
成功の成果と効果
6ヶ月間の取り組みにより、以下の大幅な成果を達成しました。
定量的な成果
- 売上の大幅向上:前年を大きく上回る売上実績を達成
- 新規顧客獲得数の飛躍的増加:従来の数倍の新規顧客獲得を実現
- 営業効率の大幅改善:1件の成約に要する工数を大幅に短縮
- 顧客情報の一元化:数千件の顧客データを統合・整理
定性的な効果
- 営業活動の透明性向上:進捗状況がリアルタイムで把握可能
- チーム連携の強化:情報共有により協力体制が構築
- 営業スキルの標準化:成功パターンの共有により全体のレベル向上
- 顧客満足度の向上:適切なフォローアップにより関係性が深化
製造業の営業DX成功の3つのポイント

この事例から導き出される、製造業における営業DX成功のポイントは以下の通りです。
1. 現場主導のボトムアップアプローチ
経営陣の一方的な判断ではなく、実際に使用する営業担当者の意見を最重要視することが成功の鍵です。システム選定から運用ルールまで、現場の声を反映させることで、自然な導入と継続的な活用が実現できます。
2. 段階的な導入による負担軽減
中小企業基盤整備機構の調査によると、中小企業のDX取り組みでは「文書の電子化・ペーパレス化」が64.4%と最も多く、段階的なアプローチが一般的です。いきなり高機能なシステムを導入するのではなく、シンプルな機能から始めて徐々に拡張していくアプローチが効果的です。
3. データ活用による継続的改善
単にシステムを導入するだけでなく、蓄積されたデータを分析し、営業戦略の改善に活用することが重要です。PDCAサイクルを回すことで、投資対効果を最大化できます。
製造業DXの現状と課題
実際の統計データを見ると、製造業のDX推進には以下のような現状があります。
DX取り組み状況
- 中小企業のDX取り組み率:31.2%(中小企業基盤整備機構調査)
- DX成果実感率:76.7%の企業が何らかの成果を実感
主な課題
- IT人材不足:28.1%の企業が課題として挙げる
- DX推進人材不足:27.2%の企業が課題として認識
- 予算確保の困難:24.9%の企業が課題として指摘
これらのデータからも、適切なサポートを受けながら段階的に取り組むことの重要性が分かります。
まとめ
製造業における営業DXは、正しいアプローチで取り組めば確実に成果を上げることができます。今回ご紹介した想定事例が示すように、失敗を恐れず、現場の声に耳を傾け、段階的に取り組むことが成功への近道です。
重要なのは、DXを目的ではなく手段として捉え、最終的な目標である「売上向上」「顧客満足度向上」を見失わないことです。
統計データが示すように、約8割の企業がDXによる成果を実感している一方で、IT人材不足などの課題も明確になっています。貴社でも営業DXに取り組まれる際は、今回ご紹介した3ステップを参考に、まずは小さく始めることから検討してみてはいかがでしょうか。
DXは「魔法の道具」ではありませんが、適切な準備と段階的な取り組みにより、必ず成果につながる投資となります。
※本記事は当社の複数の支援実績を基にした想定ケースであり、特定の企業の実績を示すものではありません。